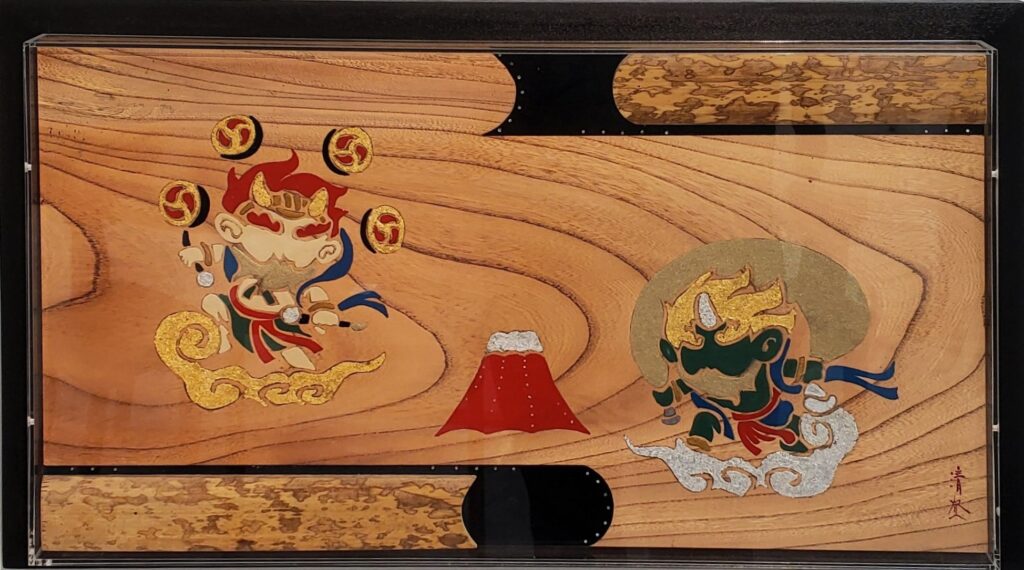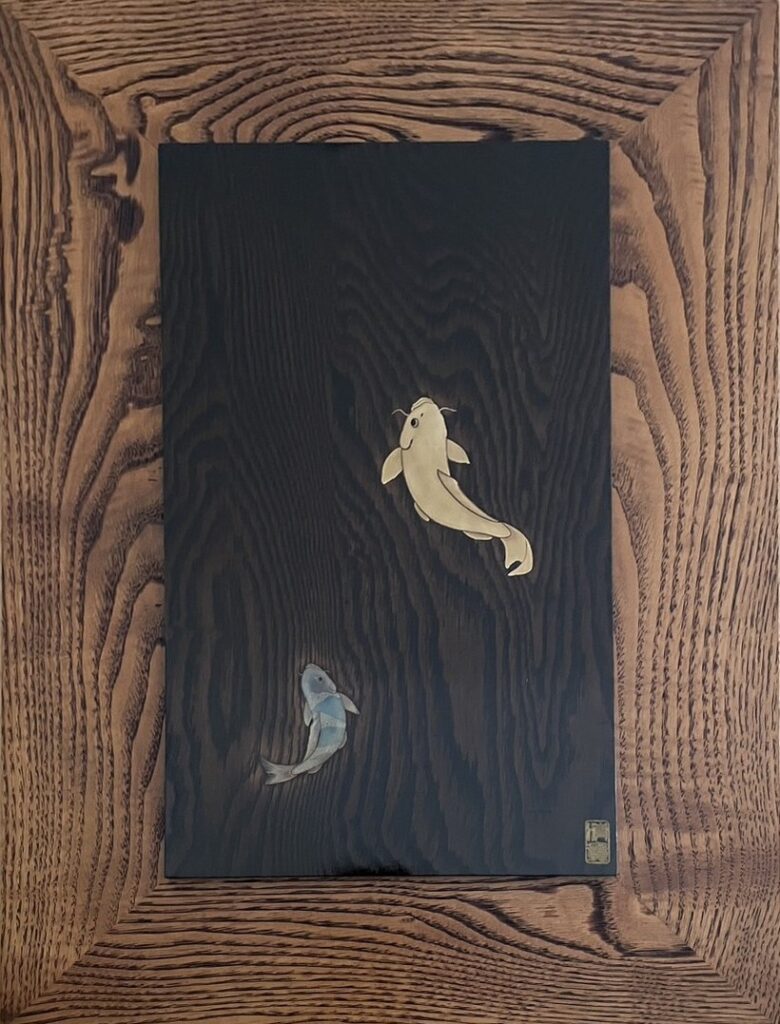びわ湖が一望できる滋賀県大津市木戸の「日の出窯」の岩崎政雄さんは、陶芸一筋50数年の陶匠です。

埼玉県出身で京都で陶芸の修行を積み、大津に自身の窯を興して以来、ただひたすらに作陶され続けました。

そして切り拓かれた境地が釉薬のちぢれを美として作品に生かした『龍爪梅花皮』(りゅうそうかいらぎ)の世界です。

このちぢれは梅花皮(かいらぎ)ともいわれ、本来は釉薬の失敗作として陶芸家からは嫌われるものでしたが、岩崎政雄陶匠は逆にそれを美としてやろうと、逆転の発想から試行錯誤しながら約10年をかけて現在のフォルムを完成させました。

特に赤の梅花皮は世界的に非常に珍しく一部のファンに世界初といわれ、長年の努力が本人が想像する以上に評価されていることに岩崎政雄陶匠はとまどいと喜びをにじませています。

現在、龍爪梅花皮作品は急須やコップなどのリビング品と大皿や壷の作品の2カテゴリーあります。




つい最近まではごく一部の限られた方にしか販売されてこなかったのですが、岩崎政雄作陶50周年を経てこれからは多くの方々に知っていただこうと、大阪阪神百貨店での個展を皮切りに、京都大丸展、東京日本橋高島屋店、岩崎政雄陶匠の地元埼玉八木橋百貨店、そして名古屋名鉄百貨店、三重津松菱百貨店(R8.1月予定)と個展を開催し、多くの方との交流の中で龍爪梅花皮作品に触れていただこうと、展示販売会を開催されています。




陶芸の歴史は数万年前の縄文時代にさかのぼります。それほど日本人の生活の中では身近な存在です。様々な諸先輩方がチャレンジされてきた新しい陶芸のフォルム、とてもそれらには及びませんが、岩崎政雄陶匠が作陶する「赤のちぢれ美、龍爪梅花皮」が、いつの日かその末席を飾れますよう、期待をもって見守りたいと思います。

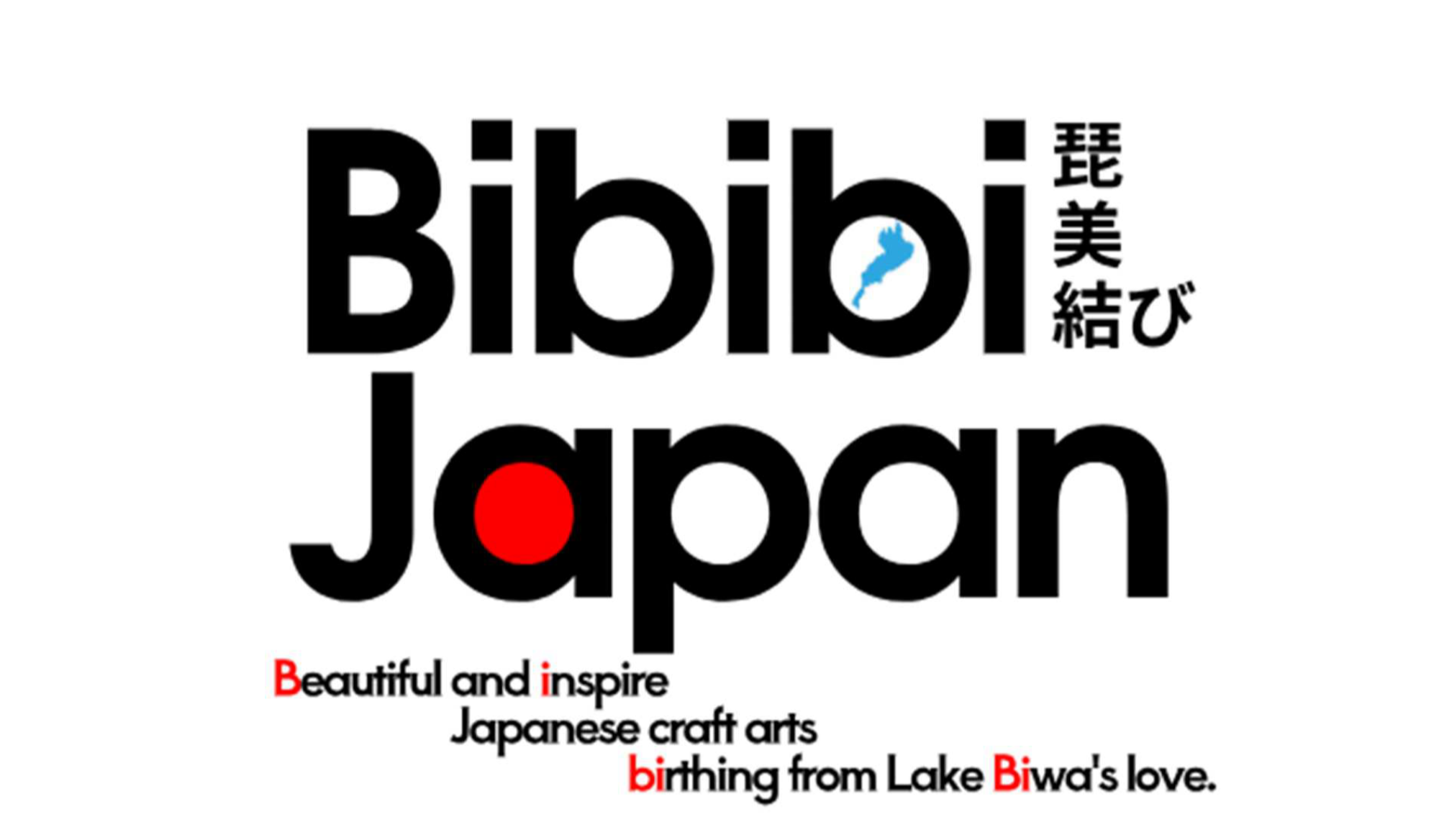

-683x1024.jpg)